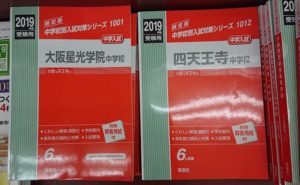難関校に合格しない「低学年で優秀だった」子供たち

難関校に合格する子はどんな子供なんでしょう?
どんな子が成績を伸ばすのか。
どんな子が目標校に合格してくるのか。
これを知っておくことは、これから中学受験を考えていく子供の親であるみなさんには、非常に重要なことだと考えます。
難関校に合格できない環境(やり方)を理解しておく
先日、教え子で、現在小学校の低学年の子を持つお母さんとお話しする機会がありました。
簡単に彼女とその子供を取り巻く環境を列挙すると
・大阪にある有名私立小学校に通っている
・幼児教室からの流れで、S学舎に今も週何度か通っている
・S学舎からの勧めもあり、中学受験のためにNという進学塾にも通っている
・毎日が、これらの塾の課題をこなしていくことに、親子が必死になって時間を費やしている
他にもありますが、割愛します。
現在、彼女のお子さんは小学校1年生。
そして、ここからが肝心ですが、
今の状況をそのまま継続させて、中学受験で最難関の学校に合格する可能性は、かなり低いと感じました。
子供の能力がない、とかそんな話ではありません。
むしろ、ご両親ともに優秀で、そのDNAを受け継いでいるので、普通に考えて「よくできる」部類に入りそうです。
ですが、中学受験では成功する可能性は低いのではないかと考えます。
その理由を以下に書きます。
・子供が自由に何かを考え、工夫し、興味を持ってやっていく時間がほとんどない。
・勉強することが毎日の義務になり、そこに面白さ、楽しさを見いだせていない。
・「自分のため」の勉強ができていない。
順に詳しく書いていきます。
子供が自由に何かを考え、工夫し、興味を持ってやっていく時間がほとんどない。
子どもは自分が興味を持った「何か」には大人が考える以上に夢中になります。
環境さえ整えてやれば、意欲的に、ガツガツとその「何か」についての知識を吸収しようと一生懸命になります。
「何か」に関連する知識や、関連する事柄に対して、自分の頭で考え、行動もできるようになっていきます。
ところが、幼少期~小学校の低学年で、「勉強漬け」になっていたら、そういった子供が飛躍的に成長する機会を奪ってしまうことになりかねません。
「何か」=「勉強」では決してない、というのが普通だからです。
自分で考え、自分で求め、行動する、これができる子は将来の伸びしろが大きいのですが、その芽を摘む親の行動は、百害あって一利なしと感じます。
勉強することが毎日の義務になり、そこに面白さ、楽しさを見いだせていない。
大人であるみなさんに伺います。
義務的にやっていることで、楽しいことはあるでしょうか。
大人であれば、「やらなくてはいけないこと」の中に創意や工夫を入れて、少しでも楽に、楽しくできる側面を見つけてこなしていくことも可能かもしれませんね。
ですが、子供、特に小学校の低学年ぐらいまでは、そういったことを子どもに期待するのは少々酷ではないでしょうか。
中には、算数の問題、特に難問を解くのが楽しくて仕方ない、という子も出てきます。
それはそれで楽しみなんですが、大部分の子は「勉強」=「いやいやながらやらないといけないもの」というのが普通です。
「塾の授業は面白いし、楽しいけど、家でやる宿題はとにかく苦痛」こういう子も多いですよね。
塾が楽しいのは「先生の話が面白い」というのもありますが、「新しい知識を学ぶこと、今まで知らなかったことを知ることが嬉しい」という面も大きい。
ですが宿題は「義務」ですから、とたんにやる気が失せるのです。強要して、無理にさせようとしても、子供には「苦痛だった」という思いしか残らないのが普通です。
スケジュールに追われていたらなおさら。決められた時間にいやでもどんどんこなしていかないといけない。
自分から「やってみようかな」と言い出すのを待つ余裕がない。
せっかく新しい知識、面白い考え方を学んできても、これではそれらを生かしきれなくなってしまいます。
すごくもったいないと思いませんか?
「自分のため」の勉強ができていない。
最後は「自分のため」の勉強になっていないこと。
ここまでのことをお読みいただいていたら、理解していただけると思いますが、「仕方なくやる」「いやいややる」というのでは、勉強を、興味深い対象、面白く感じる対象から遠ざけてしまっているのです。
結局、やっていること(やらされていること)は子供のためになっていないということです。
自分で興味、関心を持った事柄にはどん欲に向かっていくのが子供です。
それを子供から奪ってしまう「勉強」にどんな意味があるのでしょう。
優秀な子は「作られる」?
今まで指導してきた子供たちの中で、上記のような環境(させ方)で小学校の3年生ぐらいまでを過ごしていた子のうち、目標校である最難関の学校に合格できたのは1~2割程度でしょうか。
たいていの子供は、小学校3年までは塾の公開模試でも高得点を出し、成績優秀。それが、4年、5年と学年が上がるにつれ、失速していく。そして、失速したらその後容易には挽回できない。そして、その結果、中学受験においてはとても残念な結果に終わってしまう。そういうパターンが多いのです。
幼少期からたくさん勉強してきた子で、おそらくですが、半数ぐらいはそれでも「それなりの結果」は残します。
最難関は無理でも、2番手、3番手の学校には合格を取ってくることも多いように感じます。
灘を目指していたけど、結局西大和に入学した、とか、甲陽に失敗して高槻に行った、とかはよく聞く話です。
ですが、それが精一杯、あとの伸びしろがなくなってきている。こんな状態では、中学や高校でぐんぐん伸びるというのはなかなか期待できません。
そこで、親は焦って(不安を先取りして)中学入学と同時に「厳しい塾」に入れる。
または、最難関校に合格できなかったので、「次こそは」の思いでまたしても子供を追い込んでいく。
(この先、どうなるのでしょう?)
(残念ながら、お母さん方の「不安」、けっこうな確率で的中します。塾に行かなかったらいかなかったで、学校でとんでもない成績を出し続けます。)
こうやって優秀な子が作られる(ですが、残念ながら可能性は限りなく低い…)
中学や高校の勉強は、本人主体でやっていかないと意味がありません。
中学校に入ったら、勉強の主体を徐々に子供に移していかないといけません。
中学1年の1学期が終わるまでは、ある程度事細かく指示を出すのもいいかもしれません。
この段階でそこそこの結果を出すことは重要です。
ですが、子供が中学生活に馴染み、勉強についてもペースをつかんできたら、細かい口出しはやめて、本人に任せていきましょう。
親は、アドバイスはしても、余計な口は出さない。
もちろん、たまに「大噴火」して、子供の軌道を修正してあげないといけないこともあります。
でも、基本は「本人に任せる」こと。
しつこい口出しは、反発を招くだけ。
子どもの様子を見ながら(観察はしっかりやっておかないといけません)、ここぞというところで、的確なアドバイスができるかどうか、そしていざというときの「大噴火」ができるかどうか。(しょっちゅう怒っているだけでは何も解決しません。)
勉強が不調になってきたとか、成績が下がってきたとかいった事態に直面するかもしれません。
ですが、どうすればいいか、どうしたいか、しっかりと子供本人に考えさせ、自分で何とかするということを経験させましょう。
「じれったくて見ていられない」ですか、いやいや、ここは我慢です。
自分で方向付けができた子は、そこから驚くほど伸びてくれます。
小学校低学年の過ごし方に戻る