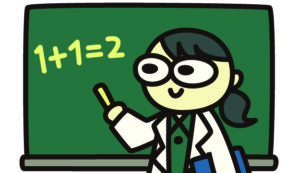大学入試改革を受けて中高でアクティブラーニング実施?

大学入試2020年問題
2017年3月末、こんな記事がdot.asahi.comに掲載されました。
『頭のいいバカはもういらない センター試験と偏差値序列社会の終焉』
大学入試が変わっていくことで、これまでの偏差値序列社会が変容を遂げていく、そして、高校以下の教育も大きく様変わりしていく、といった内容です。
めちゃめちゃタイトルにインパクトがあって、思わず読んでしまいました。
興味のある方はぜひお読みください。
まさに、今これをお読みのみなさんのお子さんたちが、この改革後の大学入試に、間違いなく突入します。
そして、2020年度大学入試改革の全貌が、徐々に明らかになりつつあります。
ポイントは、以前にも取り上げましたが、「思考力」「判断力」「表現力」を重視したスタイルに変わり、大学入試センター試験が廃止されるというもの。
改革の背景には、人口減少、グローバル化、AIの進化といった時代に対応した教育に転換しなければならないという強い危機感がある。
こういった危機感を受けての改革です。
中高の授業も変わっていくのか
当然、大学入試がこの要請を受けて変わっていけば、高校や中学の学習も変わらざるを得ません。
「受ける」授業から「参加する」授業、積極的にかかわる授業へと、中学・高校の現場は動きつつあります。
生徒たちの「思考力」「判断力」「表現力」を高めようとしていく限り、今まで通り、机の前に座って、先生がする講義をただ黙々と受けている、というだけではだめなんですね。
注目したい「アクティブラーニング」
いま注目を浴びているのがアクティブラーニング。
では、最近注目を集めている「アクティブラーニング」とはいったいどのような学習形態を指すのでしょう。
「アクティブ・ラーニング」とは「能動的な学習」のことで、授業者が一方的に学生に知識伝達をする講義スタイルではなく、課題研究やPBL(プロジェクト・ベースド・ラーニング)、ディスカッション、プレゼンテーションなど、学生の能動的な学習を取り込んだ授業を総称する用語である。(http://www.keinet.ne.jp/gl/10/11/kaikaku_1011.pdf)
つまり、生徒たちの積極的な参加なしには成立しない学習の形なんですね。
生徒たち自らが、自身の知識をもとにディスカッションやプレゼンテーションを行うことで、多様性や創造性や他者と交渉する力などを培っていき、引いては、新しい社会を自ら創出することができるように成長を促す。
大学入試で「思考力」「判断力」「表現力」を判断される、それに対応するために、中高の教育現場で積極的な活用が期待されているのが、アクティブラーニングなんですね。
ですが、これを実践していくのは、口で言うほど簡単ではありません。
単に、あるテーマについて生徒たちに思ったことを好きに議論させたり、あるいは何かのテーマを一方的にプレゼンテーションさせるだけだと、中身のない薄っぺらいものになってしまいます。
また、そのテーマについて、深い知識がある何人かは、非常に有益な議論を繰り広げたりもできるかもしれませんが、そうではない、その議論に参加できない生徒も必ず出てきます。
ですから、前提として、そこで深めたいテーマについて、生徒みんながしっかりとした知識を持っているということが必要になってきます。
考え、発言し、議論し、深め合う、これが意味を持つのは、生徒それぞれがその前提となる知識という土台を持っているときだけではないでしょうか。
今後、各中学校・高等学校は、アクティブラーニングを積極的に採用していくでしょう。
これを生かしていくことができるかどうか、各学校の進め方、考え方を機会があればご紹介していきたいと思います。
トピックに戻る