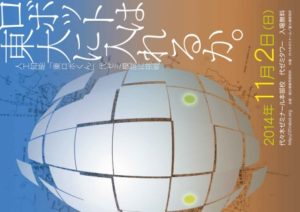灘中学合格者の幼児からの過ごし方

灘中学合格者の幼児期の過ごし方
灘中学に合格する子どもたちは、幼少期からハードに勉強しているのでしょうか?
ある調査で、実際の灘中合格者の保護者のアンケート結果が掲載されていました。
幼児~低学年における1週間の平均学習時間(学校以外での学習時間)
幼稚園
(年中):週2.9時間幼稚園
(年長):週3.7時間
小学校1年生:週5.6時間
小学校2年生:週6.7時間
小学校3年生:週10.5時間
あくまでもアンケートの結果ですから、掲載されている数値は、回答した方々の平均値であること、および、この数値には家庭学習だけでなく、塾での勉強時間が含まれていることに注意してください。
本格的な受験勉強は4年から
さて、これをお読みのみなさんは、この数字、どう思いますか?
意外と少ない、そうお感じの方が多いのではないでしょうか。
実際、今まで指導した灘中合格者の保護者と話した感触では、幼児期から小学校3年ぐらいまでは、毎日塾通いといったハードな生活をしていた子は少ないという印象です。(ま、保護者の方がすべて正直にしゃべってくれるわけではないのですが…(^-^;)
どの子も、本格的に受験のための勉強が始まる4年ぐらいから、徐々にエンジンがかかってくるという感じです。
そして、少しいい成績を取ったりすると、その成績を見て、今度は保護者のエンジンがかかってくる、そんな感じで最後まで走りきり、見事灘中同格!ということが多いように思いました。
ですから、4年以降、特に5年や6年ではもう必死にさせる(親が必死なだけではとても合格できる学校ではありません)という形になることが多いようです。
幼児期~小3ぐらいまではどう過ごしているのでしょう?
これもアンケートの結果からみますと、学習時間より子どもの好奇心を高めることに重点をおいたようです。
自然教室への参加や楽器の演奏、発表会などに参加
子供自身の興味や関心の高いことを一生懸命させる、ということでしょうか。
こういった経験を通じて、知識を深めたり、人前で緊張しながら発表するという機会を作ることが、その子の伸びしろを大きくしていくのでしょう。
親子で会話すること、一緒に読書すること
いろいろな出来事に対して、自分の考えを話させたり(保護者がちゃんと聞いてあげるという姿勢を示してあげることが大切です)、ニュースで取り上げていた内容を親子で話したり、テレビを見ていて出てきた国や地名を地図で一緒に調べるということもしてあげる。
一緒に本を読んで、言葉について理解を深めたり、出来事の感想を話し合ったりということも大切なようです。
気を付けたいのは、決して押しつけにならないように持っていくこと。一緒に調べたり、本を読んだり、話し合うことが楽しいと思わせること。
こういう取り組みは、子供の知的好奇心を満たし、さらに上を求めるように働いていくはずです。
とにかく、ふだんの生活すべてを、「自然に学ぶ」という環境にもっていってあげることが大切であると、アンケート結果が教えてくれているようです。
たくさんの経験を共有し、話をし、その中に学びが生まれると考えてください。
机の前でする「お勉強」に縛ってしまうことは、勉強すること、学ぶことを苦痛に置き換えてしまい、将来伸びるべき芽を摘み取ってしまうことになりかねません。
机の前での勉強は、本格的な受験勉強が始まる4年や5年までとっておいてもいいのではないでしょうか。
小学校入学前の過ごし方に戻る