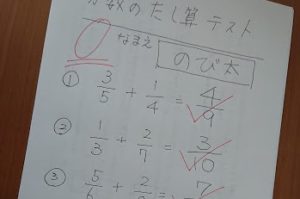家庭学習がしっかりできる子が成績を伸ばす4つの理由

家庭学習と自習室、どちらを選んだらいいですか?
子供が、塾の自習室でやりたいって言います
最近は多くの塾で、「面倒を見ます」的な指導が行われるようになってきました。
ふだんの授業でも、授業後ほぼ強制的に居残りさせて、宿題を中心に自習をさせたり、夏休みなどの長期休暇は朝から晩まで塾で預かってもらえたりします。(もちろん食事は2回分用意しないといけませんが…。)
塾側の事情もありますが、それに甘えっぱなしで、家庭での勉強が疎かになっていないでしょうか。
もちろん、塾でしっかり勉強してきてくれるに越したことはありません。それで成績を上げてくれたら申し分ないと思います。
ですが、これは
・ひとつは、塾の生徒が他の塾に流れていかないようにするため
・もうひとつは「面倒見の良さ」をアピールするため
という、塾側の事情があります。
空きの時間がたくさんあれば、その時間に他塾の講習などに参加したり、個別教室で個別指導を受けたりする子も出てきます。だって、親はわが子の合格が最優先ですから、そのためなら何でもしますから。
でも、通っている塾にしてみたらこれはできればやってほしくない。他塾の講習が気に入ったら、成績のいい子がそちらに流れていくかもしれません。
それに、お母さんやお父さんの立場からすれば、子どもが家で勉強する時間が長かったら、ガミガミ言わないといけない時間も増える。疲れて帰ってきて、そこからさらに子どもの勉強を見ないといけない。本当にストレスがたまります。
それなら、多少お金がかかっても全部塾に丸投げしたい。
気持ちは分かります。
こうして、塾と家庭の思惑は一致し、子どもが塾で過ごす時間だけがどんどん増えてくる。
でも本当にそれで力はついているでしょうか?
塾の自習室、覗いたことはありますか?
塾によっていろいろな自習のさせ方があります。
・自習室をわざわざ作って、その中で生徒に自習をさせるところ
・通常授業で使う教室のうち、空き教室を自習室として開放する塾
・授業が行われている教室の隅っこの空き机を自習用に使わせているところ
同じ塾でも、校舎によって違ったり。
監督の先生も、いたりいなかったり…
自習についての細かい指示があったりなかったり、それはもう様々。
中には、ひたすら友人とおしゃべりに興じている子もいたりします。
管理の先生が常駐せず(何せ、塾も人手不足ですから)たまに見回りに先生がやってきたら、そのときだけ「やっているふり」なんて子もいます。
ですから、子供が「自習室を使って勉強する」といっても親は油断できません。
自習室より家庭学習を充実させるべき理由
実際、成績上位の子供たちは、自習室をあまり利用しない傾向にあるようです。
そして、自習室を積極的に利用しなくても、成績を上げてきます。
その理由はいくつか考えられますが、ボクは次の4点が重要だと考えます。
1 気が散らないで落ち着いて進められる
2 自分のペースで、自分のやり方で進められる
3 親の目が届く
4 メリハリをつけやすい
「気が散らないで落ち着いて進められる」
塾の自習室には、いろんな子供や先生方が出入りします。
そういう環境だと、集中力が途切れがちになって、ついつい出入りする人の方に気が行ってしまう。勉強していても落ち着きません。
それだけでなく、先に書いた「監督のいない」環境だと、だれか一人が喋りだすと、ついついそれに乗っかってお喋りする子も出てきます。
そういう、わさわさした雰囲気の中で集中して取り組むのはなかなか難しいものです。
「自分のペースで、自分のやり方で進められる」
暗記物の勉強をするとき、ついつい声に出して覚えようとする、実際、声に出してやった方が記憶にも残りやすく、効率が良いという経験は、お母さんやお父さん世代の人もおありではないでしょうか。
ところが、自習室では声を出してやるということは、ほかの生徒の迷惑になるので、できません。
暗記物だけでなく、算数の問題を解くときでも、独り言をぶつぶつ言いながらやった方が、ヒントもつかみやすく問題に入っていきやすいことも多いもの。(私事で恐縮ですが、ボクもこの「独り言ぶつぶつ」タイプでした。)
ですが、自習室でこの「ぶつぶつ」ができないと、思うように進まなかったりします。
もちろん、本番の試験では「ぶつぶつ」はNGですが、普段の練習に有効なら、悪いことではないでしょう。
家庭でやるときには、こういったことも含め、自分のペース、やり方で取り組める利点があります。
「親の目が届く」
子供が小学校の低学年なら親の目も届いていいのでしょうが、5年や6年になっても親が監視しないといけないの?と言われそうです。
ここで「目が届く」というのは、四六時中監視するということとは別物です。
親がべったり横について、いちいち指図しながらさせる、というのはできれば小学校の低学年で卒業させてほしいことです。
そうではなくて、いつでも親の目の届く範囲で勉強している、これが大切だということ。
学年が上がるにつれて、子供自身の自我が強固に形成されていき、子供の独立心はどんどん旺盛になっていくにのが普通です。
ですから親は「必要最小限」の指示を子供に対して行ったら、あとは子供が自分で進めていく様子を「見守る」というスタンスを作っていかないと、本当の意味で子供は伸びません。
親の目の届く範囲で勉強させる、とは?
これに対して「親の目の届く範囲で勉強」するというのは、子供が違う方向に進みそうになったときに、有効なアドバイスをしてあげられるということです。
自分が何をしたいか、どうなりたいか子供自身に決めさせ(決めさせるようにもっていき)、そのために、今すべきことを考えさせたら、ある程度放置します。
このとき親ができるのは「強制」ではなく「指示」でもなく、「アドバイス」や「示唆」です。
うるさく言うことではなく、ヒントを与える。
そして、続きを子供自身に考えさせる。
実際の子供の様子を見ながら行う必要があるので、自習室に行かせている場合ではありません。
両親とも働いていたらできないのでは?
じゃ、お母さんやお父さんが忙しくしている、家を空けているなどの場合、どうすべきでしょう。
この場合も「約束すること」は意味があります。
今日、家でどんなことを勉強する、どこまで勉強する、などを話し合ったり、子供に決めさせたりして、お母さんやお父さんに時間ができたとき、こどもが約束を果たしているかどうかチェックする。
ちゃんとできていたら思いっきり褒める、できていなければ「なぜ」を問いかける。
この繰り返しを根気よく行うことです。
一方的にしかりつけるというのは、有効な手段ではありません。
「メリハリをつけやすい」
集中してやる
↓
休憩する
↓
集中してやる
↓
一緒にケーキを食べる
↓
集中してやる
↓
…
このような流れを作れるのも家庭でやっているメリットです。
特にこれから夏休み、塾での拘束時間が長くなってくる小5や小6の子供たちには、
こういったメリハリは非常に大切に思います。
もちろん、家庭での勉強場所は、できれば親の目の届きやすい場所を選ぶということも大切ですよ。
子どもの勉強をサポートするに戻る