算数で偏差値60取る勉強法
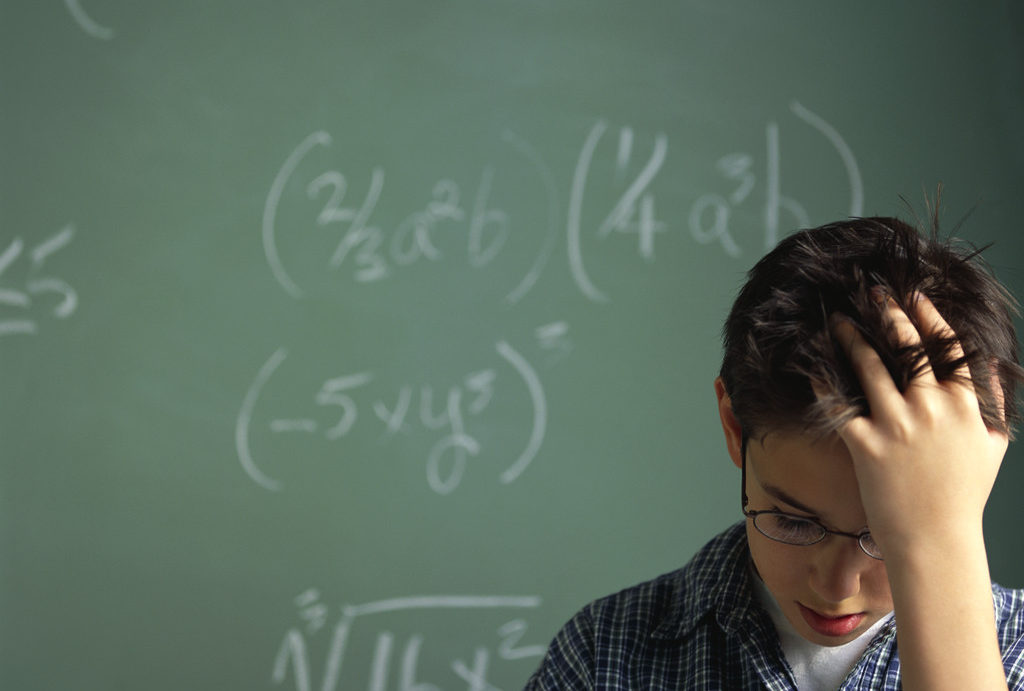
算数で6年の夏までに偏差値60をキープする。
偏差値60あれば可能性は広がる
60をコンスタントに取れていれば、関西では男子で大阪星光や西大和などの難関校が視野に入ってきます。女子でも四天王寺の医志コースや英数Ⅱは可能性が出てくるでしょう。
そのためにはどんな勉強が効果的でしょうか。
普通、進学塾で算数で大きく差が開いてくるのは4年の夏頃から。そして、差が決定的に大きくなるのは5年の中頃。
つまり、その1年間をどう過ごすかで、6年での受験校は大きく変わってきます。
では、算数のできる子はその時期どう過ごしているのでしょう?
算数で差がつく勉強方法をご紹介します。
計算問題は目的、目標を決めて毎日やる。
ただ早く計算するのではなく、途中の経過を残し、1問1問丁寧にやる、工夫を考えながらやる。これは入試を前提にした、頭を使って計算練習をやるということです。
時間はもちろん制限を設けます。
暗算が使えるところは積極的に使いましょう。
また、4年の間には、分数のかけ算やわり算までできるようになっておきましょう。
塾のテキストは1回目の取り組みが大切
2度解き、3度解きなどとよく言われます。
回数を多く解いて、復習テストに備える勉強なのですが、何も考えず二度解く意味はありません。実は、最も大切なのは「1度目」の解き方。ここをもっと戦略的にやる必要があります。
・まず、例題の復習。授業でやったことを記憶によみがえらせます。
・基本問題はできるだけ制限時間を設けて。この段階での丸つけ、間違い直しも忘れずに。
・応用問題は、そこで学んだ基本をもとに「考える力をつけていく」ためのものです。時間を多めにして考えましょう。このとき、手が止まっているようなら、飛ばして次に進むこと。ただし、あとで必ず戻って考え直します。この、「考える」ということがちゃんとできた子は伸びてきます。
ここは一番大切にしないといけない部分ですね。
・ここまでやったら、また丸つけと間違い直し。
・発展問題はすべてできなくても気にしない。1回の授業の分で1問でも2問でもしっかり考える時間が確保できるようにし、とにかく考える。
・あと1点付け加えるなら、「解説を理解する」という勉強も取り入れるといい。
ただ目を通すというのではなく、「あ、そうか!」という感覚になるまでの理解を心がけること。
⇒ 「解説を理解する」と書くと、何も考えず解説を丸写しする子も出てきますが、それは絶対ダメ。自分が理解できていないことを、ただ書き写すというのはただの作業です。
大切なことは、考える時間を確保すること。
こうした取り組みがしっかりできていれば、2度目に解くときには、全てまんべんなくやる必要がないことは言うまでもありません。
2度目は、1度目に解いたところから少し時間をおいて、次の授業の1~2日前に見直すぐらいでいいでしょう。
ただ,1度目にやってできなかったところは2度目には解けるかどうか確認する意味できちんと解きなおすこと。
考えるということを中心に問題を解くことをやっていけば、おのずと実力もついてきます。
4年の間に、次の2点ができてきたらうれしいですね。
・こういう勉強の流れとやり方を体で覚えてしまうこと。
・考えるということがどういうことかも分かっておく。
そうすれば5年の勉強にそれが生かされます。5年で内容も高度になり、量が増えてきても対処できるようになります。
最高レベル特訓への取り組みは?
最高レベル特訓などの特訓系をどうするか。
これはその子の状況次第で、選択するもよし、しないもよし、ぐらいに思っていていいと思います。
算数が好きな子は選択してもいいですが、踊らされてはいけません。
選択する・しないは子供の状況次第。
あくまでも軸足は通常の授業におき、それがきちんとできないのに特訓系の授業に手を出すことがないようにすること。
塾の経営的なことで言うと、どんどん選択させろということになるのでしょうが、そのために却って頭の中がぐちゃぐちゃになってしまい、自信があったはずの算数が苦手になってしまうケースもありますから、こういった特訓系の受講は慎重に。
塾の誘いを断る勇気も持ちましょう
塾によっては、「何が何でも特訓の授業を選択しなさい」という指導が行われるケースがあります。
管理人の知り合いで、保護者の判断で、小5、小6での特訓系の受講を断固拒否するご家庭がありました。
お話を伺うと、4年の時に勧められるまま受講し、本人の勉強のペースがぐちゃぐちゃになったので、まずは徹底的な基礎固め、と考えて、通常の授業に集中させたいということでした。
その結果、一時期低迷していた成績がぐんぐん上昇、結果的に特訓系の受講をしていた上位クラスの生徒をおさえて、最難関校の一つに合格しました。
塾からの誘い、断る勇気も必要なんですね。
6年になってもこの勉強法を継続する
基本の徹底理解とその基本を使っての応用問題演習。この2本の柱をしっかりやって行けば、塾の公開で偏差値60をキープするのはそう難しいことではありません。
そして、何度も書きますが、「考える」ということ、これを重視した勉強法を忘れてはいけません。
ちなみに、「中学受験を成功に導く無料メールセミナー」では、こういったケースも含め、塾をどういう風に利用し、入試に合格していくか、という観点からもメールの中で解説しています。
※ この記事は2014年に書いた記事に、管理人が加筆・修正をしたものです。
教科ごとの勉強の仕方にもどる
